日曜日のみことば
11月16日 年間第33主日
第一朗読 マラキの預言 3:19-20a
見よ、その日が来る、炉のように燃える日が。高慢な者、悪を行う者はすべてわらのようになる。到来するその日は、と万軍の主は言われる。彼らを燃え上がらせ、根も枝も残さない。しかし、わが名を畏れ敬うあなたたちには、義の太陽が昇る。その翼にはいやす力がある。
第二朗読 テサロニケの教会への手紙 二 3:7-12
(皆さん、あなたがたは、)わたしたちにどのように倣えばよいか、よく知っています。わたしたちは、そちらにいたとき、怠惰な生活をしませんでした。また、だれからもパンをただでもらって食べたりはしませんでした。むしろ、だれにも負担をかけまいと、夜昼大変苦労して、働き続けたのです。援助を受ける権利がわたしたちになかったからではなく、あなたがたがわたしたちに倣うように、身をもって模範を示すためでした。実際、あなたがたのもとにいたとき、わたしたちは、「働きたくない者は、食べてはならない」と命じていました。ところが、聞くところによると、あなたがたの中には怠惰な生活をし、少しも働かず、余計なことをしている者がいるということです。そのような者たちに、わたしたちは主イエス・キリストに結ばれた者として命じ、勧めます。自分で得たパンを食べるように、落ち着いて仕事をしなさい。
福音朗読 ルカによる福音 21:5-19
(そのとき、)ある人たちが、神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話していると、イエスは言われた。「あなたがたはこれらの物に見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。」
そこで、彼らはイエスに尋ねた。「先生、では、そのことはいつ起こるのですか。また、そのことが起こるときには、どんな徴があるのですか。」イエスは言われた。「惑わされないように気をつけなさい。わたしの名を名乗る者が大勢現れ、『わたしがそれだ』とか、『時が近づいた』とか言うが、ついて行ってはならない。戦争とか暴動のことを聞いても、おびえてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。」そして更に、言われた。「民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい徴が天に現れる。しかし、これらのことがすべて起こる前に、人々はあなたがたに手を下して迫害し、会堂や牢に引き渡し、わたしの名のために王や総督の前に引っ張って行く。それはあなたがたにとって証しをする機会となる。だから、前もって弁明の準備をするまいと、心に決めなさい。どんな反対者でも、対抗も反論もできないような言葉と知恵を、わたしがあなたがたに授けるからである。あなたがたは親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また、わたしの名のために、あなたがたはすべての人に憎まれる。しかし、あなたがたの髪の毛の一本も決してなくならない。忍耐によって、あなたがたは命をかち取りなさい。」
| 祈りのヒント |
| 忍耐することは、いのちを得ることです。しかし、その忍耐は自分の都合を押し通すためではなく、むしろ真実を生き抜こうとする奉仕の姿勢にもとづかなければなりません。自分の立場にしがみつかずに、ひたすら真実を生きようとして身を捧げる、いさぎよい「ゆだね」の態度こそが忍耐することの根底に潜む人間の生き方なのです。
忍耐することは、自己中心的な態度をかなぐり棄てて、ひたすら神と隣人に奉仕して、心を開く態度にもとづくものなのであり、ちょうど太陽の熱が幅広く拡散するのと似ています。それは、まさに第一朗読で「義の太陽が昇る」というイメージで語られていることに等しいものです。神の慈愛深さに満たされた真実さが「義」なのであり、神の慈愛の拡がりがあらゆるものを照らし、あたためることが、あらゆる人を悪の束縛から解放することにつながります。真実が失われた世界において忍耐するキリスト者は、神の慈愛深さの拡散を真似するかのように、悪意ある他者をも照らし、あたためます。 第二朗読で「身をもって模範を示す」という聖パウロによる姿勢が紹介されています。この姿勢もまた、自己中心的な態度をかなぐり棄てて、ひたすら神と隣人に奉仕して、心を開く態度を確認するためのものです。聖パウロもまた忍耐づよく生きたキリスト者でした。その姿勢は御父の温情や御子の寛大なゆるしを、私たちに思い出させます。 教皇フランシスコは『CREDO』(阿部仲麻呂訳・解説、ドン・ボスコ社、2022年)という講話集のなかで「忍耐づよく生きること」の重要性を強調しました。キリスト者の共同体の歴史は、まさに忍耐を積み重ねる日々だったのです。つまり初代教会における殉教者の生き方を眺めれば、キリスト者が忍耐づよく世間の悪に対処しつつも、他者を神の慈愛深さでつつみこもうとして寛大にゆるしながら、いのちを捧げ尽くしたことが明らかになります。この殉教者たちによる生き方は、まさにイエス・キリストによる十字架上のいのちの捧げ方に見習うことだったのです。御父の慈愛深さを、この社会に伝えるために派遣されて来た御子イエス・キリストこそが、にせの祈りの建物をはるかに凌駕する真の祈りの姿なのです。 |
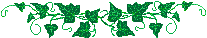 |
| (日曜日のみことば 2025-11-16) |

