日曜日のみことば
6月16日 年間第11主日

第一朗読 エゼキエル書 17:22-24
主なる神はこう言われる。わたしは高いレバノン杉の梢を切り取って植え、その柔らかい若枝を折って、高くそびえる山の上に移し植える。イスラエルの高い山にそれを移し植えると、それは枝を伸ばし実をつけ、うっそうとしたレバノン杉となり、あらゆる鳥がそのもとに宿り、翼のあるものはすべてその枝の陰に住むようになる。そのとき、野のすべての木々は、主であるわたしが、高い木を低くし、低い木を高くし、また生き生きとした木を枯らし、枯れた木を茂らせることを知るようになる。」主であるわたしがこれを語り、実行する。
第二朗読 コリントの信徒への手紙 二 5:6-10
(皆さん、わたしたちは天に永遠の住みかが備えられていることを知っています。)それで、わたしたちはいつも心強いのですが、体を住みかとしているかぎり、主から離れていることも知っています。目に見えるものによらず、信仰によって歩んでいるからです。わたしたちは、心強い。そして、体を離れて、主のもとに住むことをむしろ望んでいます。だから、体を住みかとしていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれる者でありたい。なぜなら、わたしたちは皆、キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住みかとしていたときに行ったことに応じて、報いを受けねばならないからです。
福音朗読 マルコによる福音書 4:26-34
(そのとき、イエスは人々に言われた。)「神の国は次のようなものである。人が土に種を蒔いて、夜昼、寝起きしているうちに、種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。土はひとりでに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと、早速、鎌を入れる。収穫の時が来たからである。」
更に、イエスは言われた。「神の国を何にたとえようか。どのようなたとえで示そうか。それは、からし種のようなものである。土に蒔くときには、地上のどんな種よりも小さいが、蒔くと、成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。」
イエスは、人々の聞く力に応じて、このように多くのたとえで御言葉を語られた。たとえを用いずに語ることはなかったが、御自分の弟子たちにはひそかにすべてを説明された。
| 祈りのヒント |
| 神の次元の話題については人間の言葉で適切に語ることは不可能です。それゆえに「たとえ」で物語るしかないのでしょう。神のはたらきは、人間にとっては計り知れない大きさと深さによって実現します。ということは、神のはたらきを人間の言葉で説明し尽くすこともできないのです。 私たちが子どもたちに大人の生活の話題を語るときに、大人の専門用語を用いたとしても子どもには何も伝わりません。それゆえ、私たちは子どもが理解できそうな具体例をかかげて語ることにするわけです。子どもが理解できる範囲の「たとえ」を用いて語れば、子どもはイメージを受け取りやすくなります。 イエス・キリストはイスラエルの民衆に対しては「たとえ」を用いて語りかけます。しかし、イエス・キリストは弟子たちに対しては、ひそかに解説を加えます。弟子たちがイエス・キリストのはたらきを受け継ぐ者たちだからです。イエス・キリストの生き方は弟子たちによって後世に伝えられるわけで、後継者としての弟子たちは常に懇切丁寧な解説を心の底に叩き込んでおぼえてゆかなければならないのです。 「神の国」と呼ばれている「神のおとりしきり」は、いつのまにか発展します。ひそかなかたちで、目立たずに着実に育つ「神による支えと配慮のひろがり」は人間の理解力をはるかに超えています。小さな種が巨木にまで成長するように、私たちのような小さな者たちもまた巨大な影響力をおよぼす信仰者にまで成熟することになるのです。 しかも、エゼキエル書で強調されているように、主である神こそがあらゆる者を成熟させるのであり、神の計画がひそかに進展することが旧約聖書の随所で語られています。そして、第二コリント書でパウロが描くように、私たちが生きるのは神をよろこばせるためであるのです。神のおもいを理解して成熟する人間の姿をまのあたりにするときに、誰もが大いなるよろこびを実感するのです。相手の成長を祝福して支える神の寛大な姿勢に気づかせるために、今日もイエス・キリストはあらゆる人に対して真剣に呼びかけているのです。 |
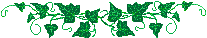 |
| (日曜日のみことば 2024-06-16) |
