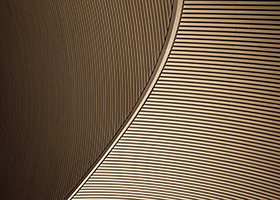 私たちは「希望の巡礼者」の聖年を歩み始めました。聖年は、決められた条件に従って祈る信徒に、教皇が特別免償を与える一年ですが、その背景には旧約聖書に記されている「ヨベルの年」の考えがあります。ヘブライ人は50年ごとの聖年に土地の安息を願って祝賀の年を迎え、それを機に負債の免除、奴隷の解放を行っていました。(レビ記25章1〜55節参照)キリスト教の歴史には、1300年にこの考え方を取り入れた「聖年」を教皇ボニファティウスの命で行ったことが残っています。
私たちは「希望の巡礼者」の聖年を歩み始めました。聖年は、決められた条件に従って祈る信徒に、教皇が特別免償を与える一年ですが、その背景には旧約聖書に記されている「ヨベルの年」の考えがあります。ヘブライ人は50年ごとの聖年に土地の安息を願って祝賀の年を迎え、それを機に負債の免除、奴隷の解放を行っていました。(レビ記25章1〜55節参照)キリスト教の歴史には、1300年にこの考え方を取り入れた「聖年」を教皇ボニファティウスの命で行ったことが残っています。私たち信仰に生きる者たちにとっての聖年は、免償をいただく特別な年ですが、一生かかっても返済しきれないほどの負債を抱えているものにとっては、人生を再びやり直す絶好の機会となったことでしょう。負債を抱え続けなければならない社会構造の矛盾を、このような方法で解消した先人の知恵が隠された営みだったのでしょう。
近代国家は、資本主義から生じる矛盾、特に富の分配の不公正さから生じる貧富の差の拡大を解消するために、税の制度や健康保険や年金などの社会政策、障害者支援や生活保護などの福祉政策を実施しています。一国の中では法の支配によってこの制度が保たれていますが、この分配の不公正さから生じる貧富の差の拡大は、国際間では放置されたままになっているのが現状です。ましてや今日、国際連合の機能が麻痺している状況の中では、さまざな条約を駆使することによって、また、国際的なNGOの活動などによって、最小限にとどめられてきた貧富の差が再び拡大する傾向となり、発展途上にある国々、そしてその国民を苦しめています。
2000年の大聖年に際して、キリスト教会のイニシアティブのもとで「ジュビリー2000」という最貧国の債務の帳消しを求める運動が展開されました。そして、今回の「希望の巡礼者」の聖年にあたっても、教皇は聖年公布の大勅書「希望は欺かない」の中で「およそ返済が不可能な国の債務を免除する決断をしてください。それは、寛大さである以上に正義の問題です」と先進諸国に願い、さらに1月1日の世界平和の日のお告げの祈りの中でも最貧国の債務免除を呼びかけました。
先進諸国の指導者たちが教皇の呼びかけに耳を傾けるようにと、心を合わせて祈ることを、聖年を過ごすこの一年の祈りの意向としてみてはいかがでしょう。